「今日は全然、聴けなかった」
こういった経験をしたことがある方は少なくないと思います。
相手の話を理解しようとしても、心がうまく動かない。
相槌がうすっぺらく感じたり、話の途中で別のことを考えてしまったり。
支援者としての自分に、がっかりしてしまう瞬間。
けれど、「聴けない日」があるのは、あなたが冷たい人間だからとか、支援者として未熟だからと決めつける必要はありません。
それは、あなたと相手の間で起こっている見えないやり取りの表れかもしれないのです。
「傾聴できない日」が生まれる3つの心理的要因
① 感情的共鳴の疲労(共感疲労)
人の話を深く聴こうとすればするほど、心は相手の感情を“なぞる”ように動きます。
それは優しさの証でもありますが、続けば心が擦り切れてしまう。
「今日はもう、誰の気持ちも受け止められない」――
そんなとき、心は無意識に“共感のスイッチ”を切ります。
それが、「聴けない日」として現れるのです。
② 役割と感情のズレ
支援者として「理解しなければ」「共感しなければ」という責任感が強いほど、自分の本心とのズレが生まれます。
「本当はちょっと苦手だ」「距離を置きたい」――
そう感じても、仕事では表に出せません。
この“内なるズレ”が積み重なると、感情が動かなくなってしまいます。
③ 自己評価への過敏さ(完璧主義)
支援者ほど「良い人でありたい」「ちゃんと聴ける人でありたい」と願います。
しかし、その理想が強すぎると、ほんの少しのミスや不調さえ“自分の欠陥”に感じてしまう。
「聴けない日」は、そんな完璧主義がひと息つきたいと訴えているサインでもあります。
「傾聴できない」のは“冷たい”からではなく、“守っている”から
誰かの話を聴くことは、とてもエネルギーを使う行為です。
ときには、心がそれに耐えきれなくなり、ブレーキをかけます。
「何も感じない」「聴く気が起きない」といった感覚は、冷淡さではなく防衛反応です。
あなたの心も常にあなたを守るために働いていて、“共感の遮断”もそのひとつの手段なのです。
それを無理に解除しようとせず、「いまの自分には心の余白がない」と気づくこと。
その気づきこそ、長く人を支え続けるために必要な心の安全装置になります。
「傾聴できない日」こそ、力動を感じ取るチャンス
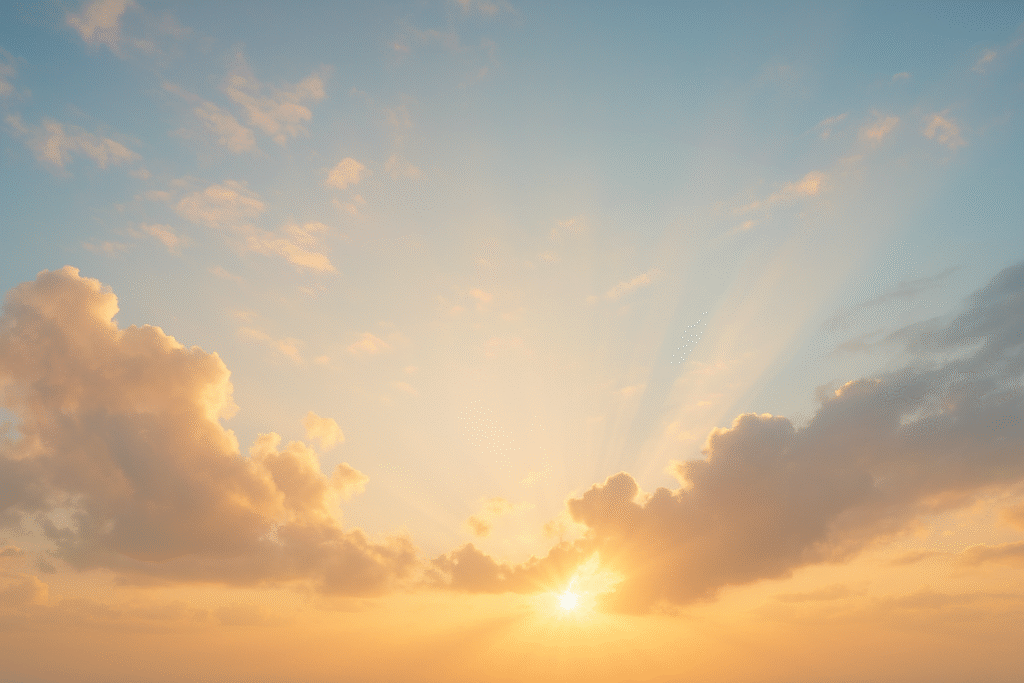
「聴けない」と感じたとき、まずは“自分の中の反応”を観察してみましょう。
- どんな言葉で胸がざわついたか
- どんな瞬間に、距離を取りたくなったか
- なぜか急に眠くなった、集中できなくなった
それらは、単なる不調ではなく、あなたと相手の間で起こっている見えないやり取りの表れかもしれません。
心理学ではこれを「感情のやり取り」や「投影」と呼びますが、難しく考える必要はありません。
聴けないときほど、“自分が相手の何に反応しているのか”に気づくチャンスです。
自分がイライラしたとき、相手の抱えきれない怒りを感じ取っている場合もあります。
逆に、無力感を覚えるとき、相手が感じている絶望を“代わりに引き受けている”こともあります。
傾聴のスキルに重要なのは、相手の話を聞く力だけではなく“自分の心がどう動いたかに気づく力”です。
その気づきが、相手との関係の“深層の動き=力動”を理解する手がかりになります。
まとめ:「傾聴できない日」も支援の一部
「傾聴できない日」は、「= 支援者としての失敗」ではありません。
それは、あなたの心が“支援の手掛かり”を与えてくれているサインであり、同時に、相手との関係の深いところを感じ取るチャンスでもあります。
自分の感情を観察できることは、成熟した支援者の証でもあるのです。







コメント