どれだけ経験を重ねても、「支援がうまくいかない」と感じる瞬間はあります。
相手に変化が見えない、関係がぎこちなくなる、あるいは自分の言葉が届かない——
そんなとき、多くの支援者は「もっと技術を磨かないと」と考えがちです。
けれど、まず初めに意識を向けるべきは“自分の感情”の方かもしれません。
自分の感情は、支援の失敗を責める敵ではなく、“いま何が起きているのか”を知らせてくれる大切な情報です。
支援がうまくいかないとき、心の中で起きていること
相手ではなく“自分の感情”が揺れている
支援が停滞しているとき、私たちは「相手が変わらない」と思いがちです。
でも実際には、自分の中で何かが揺れていることが多い。
「焦り」「苛立ち」「無力感」——
これらは支援者の中で自然に起こる感情反応です。
「うまくいかない=自分が悪い」と感じる心理メカニズム
支援職の多くは、責任感が強く、他者のために頑張れる人です。
その誠実さゆえに、うまくいかない状況を「自分の未熟さ」と結びつけてしまう。
しかしこれは、“自己評価を守るための自責”という心理的メカニズムでもあります。
自分に原因を求めることで、「コントロールできる感覚」を保とうとするんです。
支援者が抱えやすい3つの感情パターン
- 怒り:相手に対してではなく、「報われない努力」へのいら立ち
- 焦り:「このままでいいのか」と感じる不安と責任感
- 無力感:「何をしても変わらないのでは」というあきらめ
これらを感じること自体が、支援に向き合っている証でもあります。
感情を見つめることが支援の精度を上げる
感情は“判断のノイズ”ではなく“情報”である
感情は、支援の妨げになるノイズではなく、現場のリアルを映すセンサーです。
たとえば「苛立ち」を感じるなら、それは「自分が相手に過度な期待をしている」サインかもしれません。
感情を認識することで、支援の目的を再確認できる
感情に気づくと、「いま自分は何を目指して支援しているのか」が見えてきます。
「相手を変えること」が目的になっていたと気づいたら、「支援者として伴走すること」に立ち返るチャンスです。
感情を抑えるより、理解することが安定につながる
感情を押し殺して「冷静さ」を保とうとすると、支援の場がかえってぎこちなくなります。
感情は抑えるものではなく、“理解する対象”。
理解された感情は、自然に落ち着いていきます。
セルフモニタリングの3ステップ
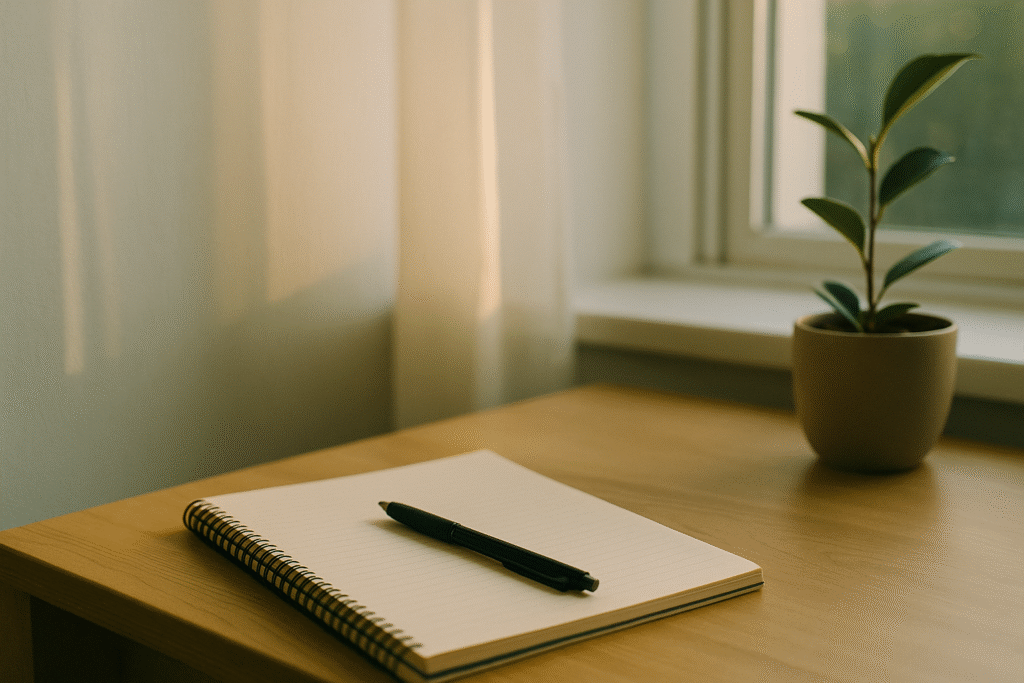
① 感情をラベリングする
まず、「いま自分は〜と感じている」と言葉にします。
(例:「焦っている」「虚しい」「期待しすぎているかも」)
感情を言語化するだけで、客観的な視点が生まれます。
② その感情の“背景の意味”を探る
その感情は、何を守ろうとして生まれているのか。
「焦り」は「相手に良くなってほしい」という願いの裏返しです。
感情の奥には、いつも“支援者としての誠実さ”があります。
③ 支援の目的に立ち返る
最後に、「自分はなぜこの支援をしているのか」を思い出す。
“変える”ためではなく、“寄り添う”ためだったはずです。
感情を見つめ直すことは、支援の軸を取り戻す行為です。
まとめ:自身の感情は、大切なセンサー
支援がうまくいかないとき、私たちはつい「もっと頑張らなきゃ」と思います。
でも、自身の感情を見つめることは“立ち止まる”ことではなく、支援の状況を適切に理解するための大切な作業です。
自身の感情を扱える支援者は、長く、誠実に、穏やかに関わり続けられる。
それが結果的に、相手にとっても安心できる支援になります。







コメント