なぜかイライラしてしまう。
落ち込んだ気持ちをすぐ切り替えたいのに、うまくいかない。
そんなとき、「感情をコントロールしなきゃ」と頑張る人は多いかもしれません。
けれど実は、感情は“コントロール”するものではなく、“理解”するものです。
この記事では、感情と上手につき合うための心理学的アプローチを紹介します。
なぜ「感情を理解すること」が大切なのか
感情を“敵”にすると、心が疲弊する
私たちはしばしば「怒り」「不安」「悲しみ」などの感情を、悪いものだと考えがちです。
しかし感情は、あなたを守るために生まれた“サイン”でもあります。
例:「怒り」は境界を守るサイン。
「不安」は安全を求めるサイン。
感情を排除しようとすると、自分の心のメッセージを聞き逃してしまうのです。
感情を理解すると、反応の仕方が変わる
感情を理解するとは、「自分が今、どんな気持ちを感じているのか」を丁寧に観察すること。
このプロセスを通じて、反射的な反応から意識的な選択へと変化が起きます。
心理学ではこれを「メタ認知(metacognition)」と呼びます。
感情を理解することは、心の主導権を取り戻す第一歩です。
感情を理解する3つのステップ
① 感情を“ラベリング”する
感情をただ感じるのではなく、「名前をつけてあげる」こと。
② その感情の“背景”を探る
「なぜそう感じたのか?」を考える。
たとえば、怒りの裏には「傷つきたくない」「認めてほしい」といった欲求が隠れていることもあります。
背景を理解すると、感情のエネルギーが“敵”ではなく“味方”になります。
③ 感情を観察するために、“距離”を置く
感情に巻き込まれすぎず、「自分の中にある一つの波」として見る練習をします。
マインドフルネスの基本はここにあります。
「私は怒っている」よりも、「怒りを感じている私がいる」と表現してみましょう。
感情との距離を置くこの作業のことを、筆者はよく「心の余白をつくる」と言います。
感情を理解することから、自己理解が始まる
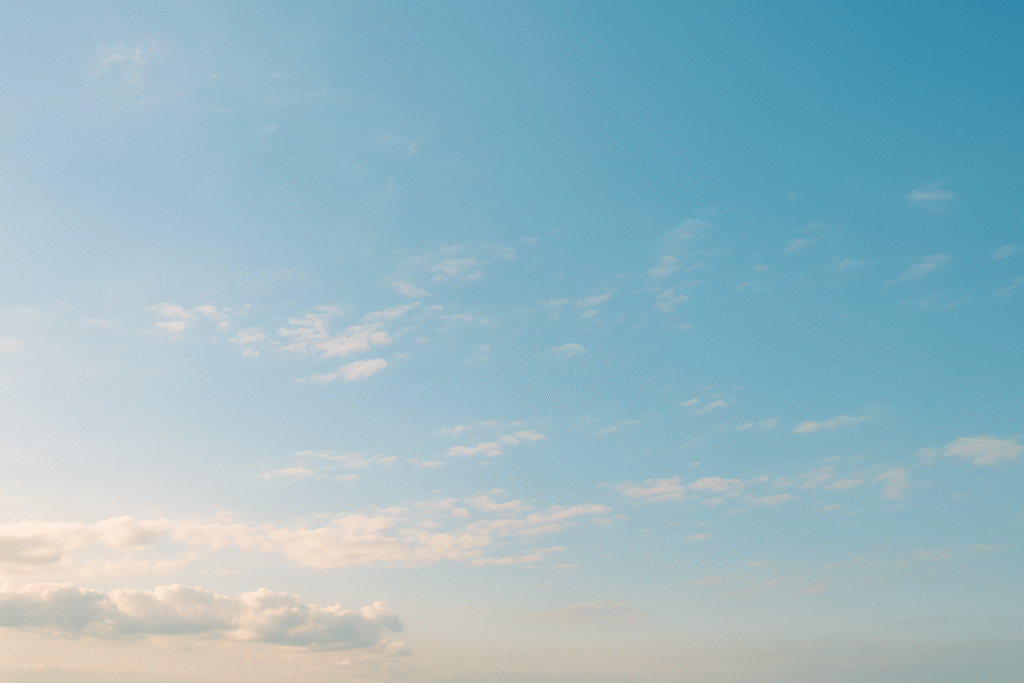
感情は、心が差し出してくれる“メッセージ”です。
その声に、静かに耳を傾けてみましょう。
感情は一時的なものではなく、あなたの価値観や人生経験の表れでもあります。
つまり、感情を理解することは、“自分を理解する”ことにつながります。
まとめ:感情を変えようとする前に、“理解”から始めよう
- 感情はコントロールの対象ではなく、理解の対象。
- 感情に名前をつけ、背景を探り、距離を取ることで整いやすくなる。
- 感情理解は自己理解へとつながり、穏やかな心の土台を作る。
終わりに
感情を押さえ込むのではなく、「知ってあげる」こと。
それが、自分を大切にする第一歩です。
今日のあなたが少しでも心穏やかに過ごせますように。

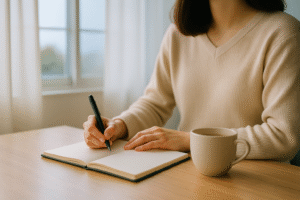

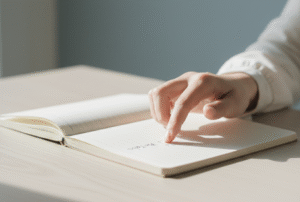
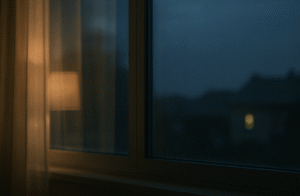


コメント